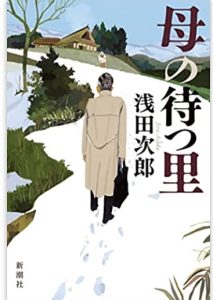母の待つ里
「ぽっぽや」以来浅田次郎の作品が好きになり読んでいる
本作はタイトルからして興味がわく、故郷には父母がいるから帰る、言えば父ではなく母に待っていてほしいと思う、そしてあれこれ世話を焼いてもらうのだ、それが母の待つ里だと思う
何とも不思議な故郷に帰ることになる三人の主人公、それぞれの「母親」観で母との時間をすごすことになる、その時間がストーリーをつないでいく。
読んでいく読者は大抵が思わずにいられないと思う、そう自分の母との時間を
罰当たりなことに自分の母親が亡くなったのは何年前だったのか覚えていない
自分が生まれた三か月後に父親は病死している、それだけでも母親の苦労は偲ばれるが自分を含めて八人の子どもを育て、農家の田畑を維持していくことの苦労は当然子どもだった自分は知りえなかった
農業に明け暮れていた母は子育てにはあまり得意ではなかったと、上の兄弟たちは言っていた
そのせいか、母親と何か親子らしいことをしてたと言う記憶があまりない、当時は小学校の運動会は家族そろって我が子の応援に来て、お昼はグランドで全校児童が家族単位でお弁当を食べていた
たぶん大抵の家族は父母がそろってきたはずだが、自分は母と二人だけで食べた覚えがあるが、何年生の時だったかは覚えていない
母との時間で記憶に残っているのがもうひとつ
幼少の頃一緒の布団に入って眠るまで昔話をいつも聞いていた気がする、今になって思うのは母はそんな昔話をいつどこで覚えたのだろう、たぶん自分も母親に布団の中で聞いていたのではと思う、すると何十年間も覚えていたことになる、それを自分に語ってくれていたのだ
残念ながら大きな記憶はそれだけかもしれない、もちろんただ忘れているだけだと思うが
仕事に就き夜間高校に通った頃はすでに家を出ていて母親との時間はほとんどなくなった、たまに帰った時には親子らしい会話になることはなかった気がする、今思うと親子関係だけでなく歳が離れていることもあり兄弟という関係も自分はものすごく薄かったような気もしている
ただ言えるのは「母親孝行」などと言うのは全くしていなかったことだと今更に思う、こればかりはどうやって記憶をさかのぼっても思い出せない、いや母親に褒められたことさえ思い出せないのだから孝行するなどという感情は持てなかったかもしれない、言い訳だが
母の待つ里を読み終え、再度目を通しながらわが身と主人公を置き換えて自分をその里に置いてみた
![]()