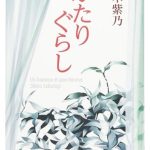紙芝居屋さん方式で「ひまわりクラブ」です
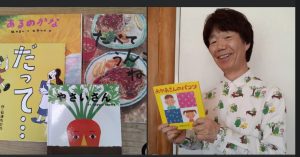
【解説】紙芝居屋とは
テレビが普及していなかった頃、子どもたちの楽しみに紙芝居がありました。自転車に紙芝居と水あめキットをつんで村々にやってきた。拠点につくと拍子木をたたいて紙芝居が来たことを知らせた。その音を聞いた子どもたちがやってきて、適当な人数が集まったら紙芝居が始まった。ただ主目的は子どもたちに水あめを売るのが目的で高いものを買った子どもは前列、買わない子供はずっと後ろでみろと追い立てられた。当時は差別やいじめなど普通に存在していたが、統率するガキ大将がいてそれなりに楽しかった。リアルで紙芝居を見ていた本人談
以下本文
小学校敷地にある「ひまわりクラブ」学校の授業を終えた子どもたちがこの建物に移動してきます
近年は高学年も通う事が可能になったようですが、全体では低学年が多いのでしょうか
この場所で絵本を読ませてほしいと営業に行ったら、代表さんが
「以前からふくちゃんの存在を知っていて、こちらでも読んでもらえないかと思っていた」
と乗りの良い明るいキャラの人で、話はとんとん進み週一回通う事となりました
ピアノさんとの絵本らいぶは以前より何か所も実績があり60分ステージをこなしていました
異学年が一緒でみんな盛り上がってくれました
今回実施するにあたり、どんなパターンにするかという事で、回を重ねてベストな方法を
見つけて行こうかとなり初日は
紙芝居やさん方式となりました。拍子木は打ちませんが、部屋の隅で数人に対して読み始め
見たい子どもたちが集まってくる・・・・というスタイルです
ピークで100人以上がいます、たぶんそうかなとは知っていましたが、子どもの数が多い
のです、いや室内が狭いと言えるかもしれません
そして集まった10人ほどは
やはり低学年、たぶん1~2年生
そしてそしてやっぱり
絵本に慣れ親しんでいると思われる
つまり
家で親御さんに少なからず定期的に絵本を読んでもらっている子どもたち
が集まって来てくれたのです
知っている、興味がある
そう思える子どもたちが集まるのです(と思っている)
絵本講座では未就学児のいる世帯で日常的に親子が絵本を楽しんでいるのは
子育て世帯の20%程度ではないかと話しています、現状もあまり変わらないと思います
つまり「絵本を読んでもらう楽しさ」を体験していると思われる子どもたちは
全体から見れば少ないという事です
想定内なので面白い事がわかりました
絵本よりはゲーム
絵本よりはコミック
絵本よりは玩具
と上げて言ったらきりがありません
そのことを垣間見ることが出来たのです
つまり絵本より楽しい事はいっぱいあり、体験しているのです
だから今更絵本など読んでもらう必要なんてない
と思っているかどうかは想像ですが
さーこれから紙芝居やさんの前に集まる子どたちが増えていくのか
それとも定数が集まるのか、楽しくなりそうです
![]()