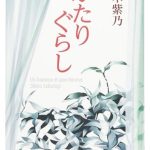きましたー
[[pict:symbol4]]
先日初めての飛込み営業をした当地の子育て支援施設の代表さんから電話がきました、先日は会えなかったのですが今週末に運営会議のようなものがあるので出席してみませんか?さらに11月初めに絵本を読んで見ますか?
とのお話でした。
おおおー苦節?年ついに出番が来そうです、本当にデビューするかも知りません!!!
本が消える?
[[pict:nose6]]
地元紙によれば当地の市立図書館で年間3000冊余りが行方不明になっているという事だ。
無断持ち出し、つまり万引きと借りた本を返さないものがこの数字になっているらしい、初めて知ったこの事実です。
利用者のマナーなどと言えばそれまでだが図書館を利用する人達にも悲しいかなマナー違反をする人がいるんですねー
返却をしない人には三度まで督促状をおくるのですがその費用がこれまた年間36万円かかりそれでも返さない人には以後は何も策はなし。
図書館の本は自分達の税金で買っているわけなので回り回れば結局自分達の負担になっているのですがそのことには気がつかないのでしょうか
日頃図書館にはとても感謝をしている身にとっては何とも悲しい記事でした。
営業活動開始?
![]()
当地にある「子育て支援施設」に読み聞かせボランテァの志願の営業行ってきました。
今日は代表の方とは直接会えなかったのですが、電話で話をして「読んでもらえる雰囲気と感じたらお願いしたい」と言ってもらえました、アポの電話の時は「何でしたら当日読んでもらえますか?」と言われていたので何冊か用意はしていったのですが、今日はなしでした。
そこでどうせなら夢を大きく「めざせ読み聞かせ100ステージ」と言うプログを別に立ち上げることにしました。一体目標にはいつたどり着けるのかはたまた頓挫するのか、やってみたいと思います。
このプログのリンクから飛んでいけるようにしましたが、初ステージはまだです、楽しみですねー
読み聞かせ デビュー
![]()
今日は講座主催図書館が通常の告知で募集した子どもたちの前での読み聞かせデビューの日でした。
自分のグループは五人が担当して二番目に「ろくべえまってろよ」を読みました、生憎の雨模様だったのですが9人の子どもたちが聞きに集まってくれました。
自分の読み聞かせを録音すべくボイスバーも準備してスタンバイをします、最初の人の絵本は短い話だったのですぐ順番となり絵本を手に前に出ます、最前列にみごとに横一列に並んだこどもたちは1〜2年生のようです、さすがにみんな聞きなれた子どもたちのようでみんな「聞きモード」の体勢を維持しながらじっとこちらを見ています。
ろくべえ・・・は実習でも読んでいましたので比較的落ち着いて読むことができました、二ヶ所ほど間違いましたが子どもたちから笑い声も聞こえたのでこちらも少し安心しながらの読み聞かせです、終わったときには拍手をもらい心の中では「やったぜ」てな事でデビュー終了です
他のメンバーの方も本番に強くなかなかの出来だと思いました、聞いてくれた子どもたちと一緒にいた何人かの大人の人はどんな風に今日の読み聞かせを聞いてくれたのか興味のあるところです。
ここでどんぶらこっこ さんがアドバイスしてくれたように今後の読み聞かせ現場を捜すために講座受講生の人たちに手製の名刺を配布してアピールをさせていただきました、このブログのアドレスも書いておいたのでこちらも見てくれるかもしれません。ちなみに名前の冠は
「読み聞かせ修行人」といたしました
本日をもって講座関係は全て完了となり今後は独力で読み聞かせの実践に突入したいと思います。あー無事に終わって良かった。
監禁?
![]()
風邪ぎみのようで頭がふらついていたので昼寝をしたら夜眠れなくなってしまいあれこれ考えていたら突然思い出してしまった。
10月2日にいよいよ講座主催図書館で子どもたちを募って受講生が「読み聞かせ」をすることになった次第です、で先回の打ち合わせで
当日参加の受講生の役割が「司会?」と「ドア係り」と言うのがあって確かドア担当は
「読み聞かせが始まったら出入りできないように鍵をロックしてください」とか説明があったような気がします。
その時は同じグループの人たちと何を読むのか相談していたのでちょちょらに聞いていたのだが思い出すとそうだったよう気がします。
講座の中でも「読み聞かせ中は出入りをさせないようにしましょう、聞き手の集中力が途切れます」と教わりました。
でもこれってかなり強引ですよねードア係りがいればその人が出入りをできないようにお願いすればいいわけで、ロックをする必要はないでしょう
幼い子どもたちはこのことには気がつかないと思いますが一緒に来た親(これも会場によって親の同伴の可否があるようですが)やそして自分もですが違和感を感じる人もいると思いますが・・・
緊急事態の時にはパニックになり簡単な施錠を開けられないと言う話を聞いたこともあります、ロックするなら緊急時の別の出入り口を事前に説明することも必要ではないでしょうか、それより「読み聞かせ」をするのに結果的に監禁をしてしまうように出入り口をロックする必要はないんじゃないかなー
こんな事を考えていたらますます眠れなくなった・・・