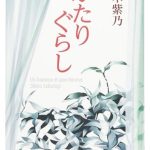子どもはまた産めばよい

映画「母性」
母親に愛能う限り(あいあたうかぎり)と育てられた娘は自分も母になった
そして事件の時は自分の子どもより母親を助けようとする
母は娘をとがめるが、娘は言った
「子どもはまた産めばいい」と
我が子よりも自分の母親の命を優先するという母親のこの言葉はかなりショッキングであり本作を象徴しているシーンではないかと思った
母親→娘→その子ども(娘) とつながる子育ては傍目に見ると不思議な光景だが「子育て」という観点から見るとやはり首をかしげたくなることが多かった
母と娘、その子育てには父親が登場しない、実際には存在するのだが影響が見られない、そんな父親も居場所を求めて妻と娘を裏切ることになる
母性とは何か、女は娘になるし母にもなる
原作を読んでいたので母娘の描写がどこか足りない気もしたが、映画なりのストーリーとなったのではと思う、映画は見たが原作を読んでいない人にはぜひ原作もおすすめします
母娘の関係とは

映画「わたしのお母さん」
母娘の関係はとても良いパターンと複雑な関係性になっている場合がありそうです
仲良し母娘で良く旅行に行く、などの話はよく聞くことがあります
同じように実母が苦手だという話も聞いたことがあります
本作は微妙な母娘の関係が淡々と子ども時代と現在が行きつ戻りつ展開していきます
「子育てを間違った」などと我が子にどなる親は今や論外と思われますが、根っこに子どもへの愛情のようなものが育たなかったゆえなのかとも思いました
母親ひとりで三人の子育ては母にとっては決して楽しい子育てにはならなかったのでは、とも思います
子ども時代のシーンに、学校から急いで帰って来た娘が、仕事に行く母親に抱きつくも振り払われてしまいます。この場面の必要性は何だろうかと考えました、ひよっとすると母親の愛情のバロメーターとして描かれたのでは、と思いました。
仕事に出かける前に一緒に絵本を一冊楽しんでから仕事行く。なんてことが出来たらこの話は別のものになっていたかもしれませんね
12/25日(日) イオン新潟西店で絵本らいぶです


【告知です】
クリスマスイベントです、親子で・大人だけでも楽しめます
イオン新潟西店のイベントスペースにて絵本らいぶピアノ付ver 開催です
場所 イオン新潟西店3Fイベントスペース
日時 2022年12月25日(日)
一回目 11時~12時
二回目 13時~14時
入場無料
がっきの店あぽろん主催
No1068 しゅくだい読んたら宿題になった

地域の小学校です
久しぶりに一年生ですよ、学校で絵本を読むと学年別の子どもたちに会えるので成長度が楽しめます、保育園でもそうですが、子どもたちは日々成長しています。
今日は「しゅくだい」です。抱っこをしてもらう宿題に一年生の反応も面白いです
終わった後にハグしてもらっているかと聞いたらみんな、やだーと答えてくれました。そうか一年生は父母にハグをしてもらわないのかな
それを聞いて先生が「今日の宿題はハグしてもらうことにしようかな」と返してくれました、なかなかウィットにとんだ先生ですよ
終わってからボランティアの皆さんと各種情報交換というお茶タイムです、面白いお話もでますね
こっちの方も楽しみなんですね
2021 年6月以前の絵本らいぶ記録ブログは こちら から
No 1067 歳で盛り上がった3年生
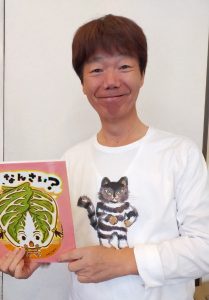
地域の小学校 今日は3年生の担当です
三年生は何をしているときどんな時が一番楽しいのか、そんな質問に答えてくれました
いろいろ出ましたが、なるほど~ですね
この絵本、シャツれっけのあるお話です、ページをめくって即反応できたら偉いですね
盛り上がり、隣のクラスの担当さんが後で、ふくちゃんのクラスは楽しそうたった、と教えてくれました
それならばボランティアさん一同が戻ってきたところで、この絵本を披露とのことで読ませていただきました、大人の皆さんも楽しんでもらいました
そのあとそれでは自分もとお二人から今日の絵本を読んでもらいました、だれかに読んでもらうと楽しめるのが絵本ですね
帰宅後気をよくして、ゲストを交えて再度読ませてもらいました、朝から三回同じ絵本で楽しんでもらいました
2021 年6月以前の絵本らいぶ記録ブログは こちら から