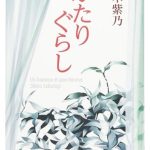「新生活様式」での読み聞かせ
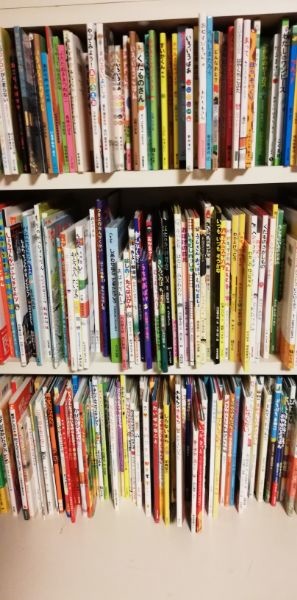
【画像は出番を待つ我が家の絵本達】
コロナウイルスの影響で絵本の読み聞かせ
にも影響が出ている
自分も3月から全く絵本を読まない生活に
なってしまった
「新生活様式」なる言葉が発表されてから
読み聞かせにも影響が出てくるようになった
そもそも三密状態は避けなければならない
ので集団への読み聞かせは出来ない
自分は「わが子に絵本を読んであげなかった」
ことを看板?にして子育てには絵本を読んで
ほしいとの思いを「絵本らいぶ」「絵本講座」
で伝えることを15年間続けてきた
そんな経緯で自宅で子どもを抱いて絵本を
読む経験・体験を全くしないまま
いきなり保育園の年長クラス30人に絵本を
読むことからスタートした
その後書店・子育て支援センター・デーサービス
保育園・幼稚園では子どもたちだけではなく
親子が100人以上集るときにも絵本を読んでいた
いつもいつも「集団」への読み聞かせが主で
10人以内程度の人数向けは少ないのです
コロナウイルスの影響で「集団」という現象
を避けなければいけない世の中になり気がつきました
自分は
「絵本の読み聞かせ」はいつも集団の中でしていた
ことを
3月から読み聞かせが全く出来なくなり
自身のフラストレーションはかなり溜まって
しまいました
話は変わり
全ての子育て世帯で日常的に子どもに絵本を
読んであげるようになっていたら、自分は
必要とされていなかったかもしれません
わざわざ絵本を読むだけの人を呼んで
読み聞かせなどしてもらわなくても
良かったかもしれません
さらに世に活躍している「読み聞かせボランティア」
さんも登場しなかったかもしれません
発想を変えれは
集団でいることができなくなり
大勢への「読み聞かせ」が出来なくなった
今こそ家庭で絵本を楽しんでほしいと
思うのです
本来の絵本の役割と言える
「お家で親子が楽しむすがた」
このことにみんなが気がついて
絵本を楽しむ家庭が増えれば
読み聞かせの機会がなくなった
などと自分は嘆くこともないのではと
思う
そうなればきっと
子どもたちが過ごしやすい家庭や社会に
なって行くのではと希望する
絵本は人と人を結ぶものだった
新潟県の旧・西蒲原郡 巻町にある地域FM
の番組に時節柄zoom 出演させてもらいました
地域FMとは言え、こうしてyou tube にup
してもらうと世界中から見れます
もはやエリアは無いに等しく
技術の進歩に驚くばかりです
インタビュー形式のゲスト出演は
相手が自分の持つものを引き出して
くれるので面白いです
話す予定ではなかったことも
つい話してしまうことがあるのも
ナビゲータさんの持ち味ゆえです
あとで見ていたら(聴いたら)
リモート読み聞かせが出来にくい
(諸々の事情で)
との話をしていましたが
著作権申請をして許可を得て
読みましょうね
との意味です
聞きかじった「公衆送信」などの
言葉も聞きなれないと思いますので
興味ある人は調べてください
今回出演にあたって過去15年のブログ
を読み直しています
自分の記録として書いていますが
結構役に立っています
3月4月と全く絵本を読みに出かけられなく
なり、気がつきました
いかにたくさんの人たちに助けられていたのか
改めてわかりました
絵本らいぶを開催してくれた皆さん
絵本講座を主催してくれている
行政・団体・施設の皆さん
書き出すと書ききれないほど多くの
人たちに「絵本」でつながってもらいました
15年前絵本を読みたいとお願いしたら
公立保育園の園長先生を紹介してもらい
毎週年齢別クラスに通よわしてくれた
園長先生
そしてその保育園に勤めていた先生の
転勤先に次々にふくちゃんを呼んでくれた
多くの保育士の皆さん
絵本を読み始めた時には、どうせ
そんな続かないだろうと挫折防止に
「めざせ絵本の読み聞かせ100回」
のブログを立ち上げ、あっという間に
2年間で100回を達成できたのは
この保育士のみなさんのおかげです
おかげで記録として書いているブログ
二本は15年間今も続いています
ひとつはこのブログ
もうひとつは名前を変えて
絵本楽語家 ふくちゃん になりました
今回のナビさんとの出会いも絵本が
つないでくれました
とあるパーティーで偶然同じテーブル
となり名刺交換を作るしたのが縁となり
アナウンサーさんとのことで絵本も読んで
いてふくちゃんとのコラボも仕掛けて
もらいました
食べ歩きレポブログは素晴らしく
美味しい物に困ったらこの人のブログ
を見ています
交友関係が素晴らしく人材に困らない
のではと思われます
今回の番組もそのネットワークを駆使
して何年も続きそうですね
絵本は親子ふれあいのコミにケーションツール
と講座で話していますが、親子だけではなく
人と人を結んでくれるツールだと思います
あまり信用されませんが、人とのつき合い
が苦手な身ですが15年間絵本を読んで多くの
人たちと関わってこれたのは絵本のおかげと
思いました
コロナウイルスでこれからは
「新生活様式」とのことで
併せて個人の価値観などが問われて
変わっていくかもしれません
そんな中、絵本は人と人を結んで
くれると確信出来ました
そんな事を思いおこすきっかけとなった
今回のラジオ出演でした
大変ありがとうございました
テレビ電話

画像は以下のサイトです
「テレビ電話」などと言うと歳が知れる
今や死語と思っていたら、ありました
コロナウイルスで外出自粛となった近頃
テレワーク・リモート会議・zoom
など世代によっては耳慣れない言葉が
連日聞こえてきます
これらの新しい道具もテレビ電話と呼べ
なくもありません
まだネットなどがない時代に夢の電話機
ということで相手の顔が見える電話機
が発売されたか、発売できる、などという
ニュースがあったような気がする
たぶんアナログ電話回線かその後のISDN回線
を使い音声信号の中に静止画を何秒間隔で送る
ものだったかもしれない
ところがこれが売れなかったようだ
ギャグのような話だが
顔が見えては困る
となったらしい、理由はそれぞれ考えて欲しい
夢の技術はいとも簡単な理由で世間に認められな
かったのだ
そして時代が変わり
コロナウイルスの影響もありテレビ電話
がにわかに一般の人に知れることとなった
スマホを使いこなしている世代には今更感
があるだろうが切実な悩みを持つ人もいる
遠方の施設に入院している親族のお見舞いに
行きたいが施設は見舞い禁止となっている
さらに外出自粛で電車に乗るのもはばかられる
と相談された
これを読んでいる人たちは、すばやく解決
方法をイメージできるが、そうではない人もいる
まず
スマホを買う・セットアップする
使い方レクチュアー・スマホで電話が使えるまで
アプリを入れる・テレビ電話が出来る
これでようやく、テレビ電話ができるようになる
この流れをだれかが優しく丁寧に
教えないといけないのです
テレビ電話は今こそ出番です
そしてスマホ・PCとは無縁な人達が
自宅に居ながら遠方のそして近所の人達と
「遠隔お茶飲み」ができるようになって
ほしいものです
スマホを持っていてもLINE アプリは
入ってないし使い方も知りません
近所にはたくさんいそうですね
そんな皆さんに手を差し伸べてほしいものです
まずは自分もおぼえます
あんなこんなの話もしたネット番組
インターネット番組に出演しました
収録場所が新潟市の唯一の地下街でした
往年の賑わいが懐かしい場所ですが
日曜日の昼時静かな雰囲気で収録にぴったり?
調子に乗り結構言いたい放題
絵本の勉強はしない方がいい
などと言ってますが
これから絵本を読もうとしている子育て
開始のママさんは読み聞かせの情報を
集めると、その情報の多くは「読み聞かせ会」
などでの多くの聞き手に読む場合のものが
多く、我が子を抱っこして絵本を読む場合
それらのことは気にしなくて良いという事です
絵本についてひたすら学びを追求したい人に
向けて言っているわけではありません
などと言い訳をするくらいならば
ブログにのせなければ良いと思うのですが
はい、ご容赦を
6年間続いた図書館派遣事業

新潟県柏崎市の柏崎市立図書館さん
ご縁があり6年前より図書館派遣事業
として市内の保育園・幼稚園で
絵本らいぶ・絵本講座を開催してもらい
高速道路走って60分が近く感じられるように
なりました
6年間で絵本を楽しんだり絵本による子育て
の大切さを知ってもらった大人・子ども達は
通算約1600人となったとのことでした
同じ行政さんの事業で継続して行ってもら
ったことはとても意義深いことでした
印象に残っている保護者さんの言葉で
絵本講座に参加して
「こういう話をもっと早く聞きたかった」
との感想でした
絵本講師として話していることが役に立っている
ことを実感した出来事でした
子ども達とはたくさん絵本を楽しみました
複数回訪問した保育園もあり園長先生からは
いろんなお話を聞かせてもらいました
担当者様・館長様 大変ありがとうございました
これからもこのような事業が続くとうれしいです