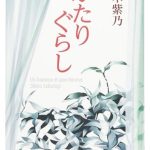先生も悩む?
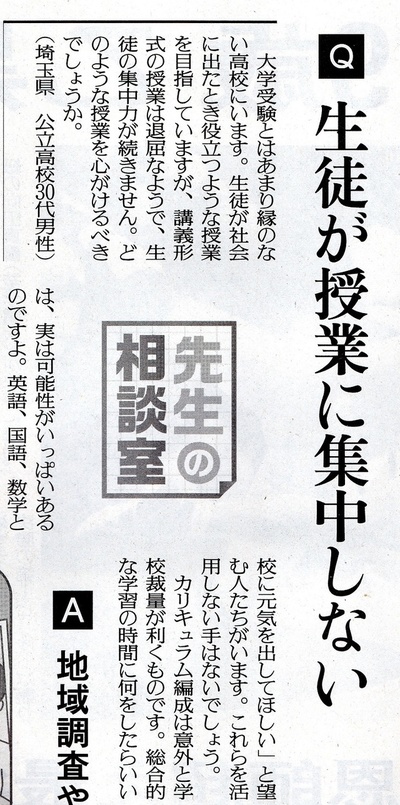
2018/10/24 読売新聞
先生の相談室
先生も悩むようでこうやって相談するんですね
「授業に集中しない」
わが身を思い出してしまった
中学校時代の数学を始めとするほとんどの授業
は全く理解できず集中するなどあり得ない状態でした
かといって私語や騒ぐこともできず
ただただ難行苦行の毎日でした
よってテストで零点は何回もあり
通知表は5段階評価で煙突とガチョウさんが
並んでいました
高校の国語の先生が教科書を全く使わず
オリジナルのテキストを毎回用意して授業を
してくれて結構わかることがあり
それまで学校の授業とは自分には理解できない
と決めていたのだが、わかる事もある
わかる教え方をしてくれる先生もいる事を知った
社会人になり仕事のために使う勉強もしたが
ちっとも楽しくなくしょうがなくやっていたので
自分の役にたったのかは、いかばかりかと自信がない
以来「学ぶ」というものはそんなものと決めつけていた
月日は流れてなぜか絵本の世界に足をつっこみ
これまたなぜか人様に「話を聞いてもらう」稼業
をすることになりその学びは意外にもすんなりと
頭に入ってくることが多くある
これは一体どうしたことなのかと今更だが
驚いている
それがこうして10年以上続いている
そして心がけているのは
「相手に伝わる話」を分かりやすく伝える
と言うことです、これは「飽きない講座」をすることに
つながっているのでは思っています
そう考えるとあの難行苦行の授業時間を
耐え続けた?のはまんざら無駄ではなかった
などと自らを評しています
人生何がどうなるのかわかりませんね
福島県 郡山市での研修会講師


福島県教育委員会さんとご縁ができて
各地での読み聞かせ研修会に呼んで
もらっています
今年は郡山会場です
初めて行く郡山でしたが
絵本セラピー繋がりの人がこちらに
住んでいるとのことで連絡をもらい
前夜祭をしてもらいました
うれしい時間です
講座前日の宿泊はいつも一人寂しく
過ごしていますので
さらに講座にも参加してもらいました
そして講座は
沢山の皆さんが熱心に聞いてくれました
参加者さんが用意した沢山の絵本に囲まれて
会場内はとても良い雰囲気となった時間でした
皆さんありがとうございました
テレビの取材が入って夕方のニュースで
使うとのことでしたが果たして流れたかな〜
講師インタビューはありませんでした(笑)
後日地元の方にニュース画面をもらいました
Nさんいろいろお世話になりました
・
「うえきばちです」を読む女子中学生
2005年11月それまで読んだことがなかった絵本を
保育園で読み始めました
13年経過したことになります
絵本を読むことなどにどんな意味があるのか
などということもわからずただ毎週一回保育園
に通い年齢別クラスを回っていました
彼らがやがて成長して保育園での絵本の時間を
覚えていてくれることがあったらうれしいなー
と考えていました
そして10年経過して
先日FBで知りました、どうも自分がその保育園で絵本を
読んでいたときの子どもさんが中学生になって
自らも通っていた保育園に実習に行ったとのことです
そしてなんと何とお気に入りの絵本を子どもたちに
読んであげたらしいのです
「うえきばちです」自分も好きで時々読んでいます
もちろん自分が保育園で絵本を読んでいたので
聞いてくれた子どもたちも絵本好きになった
などということはあまりないと思いますが
少なくても保育園実習で「うえきばちです」を
読む中学生女子になっていたのはうれしい事です
この絵本「うえきばちです」が好きということは
かなり絵本を読んでいます、絵本が
身近にある生活です
この絵本を子どもたちに読んであげている姿を
想像するだけでとても嬉しくなりました
そして絵本を読むことを10年以上続けていることを
実感できました
自分が絵本を読むことで何がどうなるか
その期待は無用です、結果として有形無形として
聞いてくれた人たちの中に残っていきます
今や地域の保育園に通う子どもたちや小学生から
「ふくちゃーん」と声をかけてもらえます
我が家は保育園、小学校の近くということもありますが
なんてうれしいことです
「絵本がつなぐ子どもと大人」
もちろん 「絵本がつなぐ親と子」にもなります
絵本を読んでいるだけでこんな幸せがもらえます
父親になった日
あることがきっかけで自分の子どもが生まれた時の
事を思い出した、
今思いだしても結構ショッキング
な思い出として記憶に残っている
もう30年以上前の事です
わが子が生まれた時に同室には何人かの新米お母さんが
いた、
あるお母さんが授乳後こどもを新生児室に戻そうとし
て赤ちゃんを抱いて廊下に出たとたん、
ものすごい剣幕で看護師さんか助産師
さんから強く叱責されていました
赤ちゃんをお母さんの胸に抱かずに、
何かとても重い物を持つかのような
しぐさで自分の体から離して両手で抱える
ような持ち方で、
傍目で見ても頼りない抱き方?だったのです
その叱責を見て自分は
「あぁ赤ちゃんはそんな持ち方をしてはいけないのだ」
と学んだほどです、
とはいえわが身の胸に抱きかかえるように
わが子を抱いたのは自分は結構あとから
だったように覚えています
専門職の方は知っているので熱心に伝えるほど
出来ない人・知らなかった人は
「強く言われた」
「叱られた」
「自分はダメな人なんだ」
と言う風に捉えてしまいかねません
最近聞いた話ですが保健師さんや助産師さんが苦手
と思うママさんがいるとのことです
知っていることを専門的な立場で教える
ややもすると聞き手の立場からは
叱られた・否定された、と思うこともあるかも
しれません
知らない人にはその人に寄り添うように教えてあげる
絵本講師は「教える人」ではなく「寄り添う人」と
教わりました、人様に何か伝えるときには心がけて
いることです
自分がおとうさんになった気がするのは
抱いたとき小さな手が
自分をつかんでくれたとき
と記憶しています
絵本は絵を読むもの
思われる赤ちゃんを抱っこして
絵本を読んでいるお母さんがいました
絵本にはその施設の名前が書いて
あるので自分が持ってきた絵本
ではないのでしょう
すぐ隣にいたもので聞くとはなしに
絵本を読む声が耳に入って来ました
そして何か違和感を感じました
お母さんは普通に絵本を読んでいたのです
その絵本は赤ちゃん向けと思われる
でも普通に読んでいる
「普通に読む」とは?
例えて言えば多少誇張になるが
新聞を読んであげているようなもの
平坦で抑揚のない読み方
「読み聞かせ」の方法について
学んだことのある人ならば
一度は聞いたことのある読み方です
でも「平坦で抑揚のない読み方は」
読み聞かせ会などでの
読み手1:聞き手多数
の時に使う読み方なんです
このお母さんは家ではどんな風に
あかちゃんに読んでいるんでしょうか
自分の家にある絵本ならきっと
こんな風には読まなかったかもしれません
一例として
画像の絵本「いないいないばあ」
この絵本を手にして赤ちゃんに読めば
自然と「いないいないばあ」をしながら
読んであげることになると思います
そう、それは「平坦で抑揚のない」読み方
にはならないのです
最近はこの「いないないなばあ」をしない
お母さんもいると聞いた事がありますが
知っていればこの絵本は赤ちゃんと
やりとりをしながら読めるのです
文字を読むのではなく
「絵」を読んでいるのです
わが子を抱っこして絵本を読む時は
「語りかけ読み聞かせ方」
で読んで欲しいものです
絵本を使って親子が遊ぶ
そんなイメージです
絵本は文字を読むものではなく
絵を読むものです
特に赤ちゃんに読む場合は
知っていてほしいですね
お子さんと出かける時には
お出かけセットにお気に入りの絵本を一冊
ぜひ入れておいてほしいものです